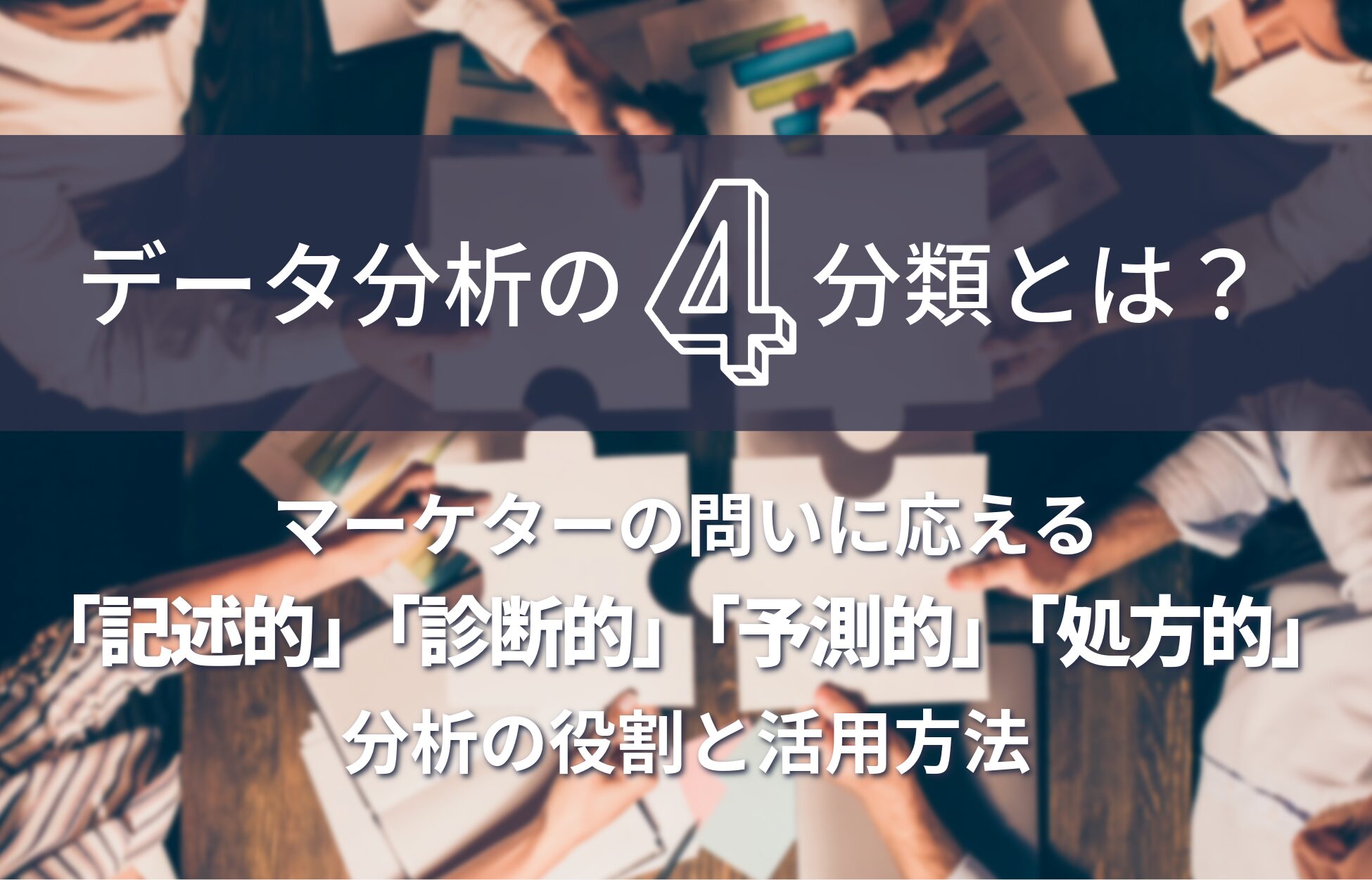なぜ、データドリブンなはずの施策が空振りするのか?「顧客の本音」を行動経済学で解き明かす
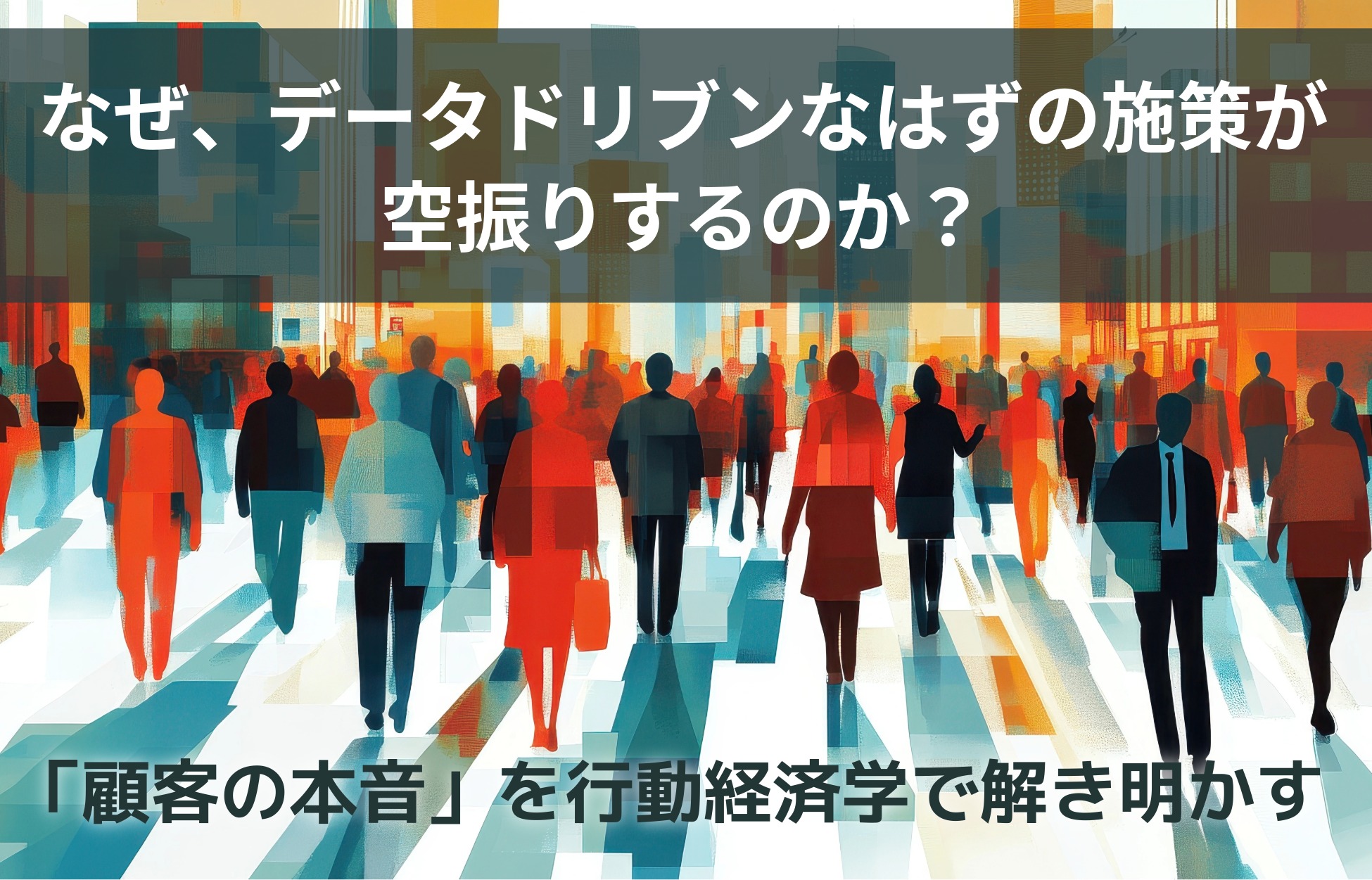
データがあれば、マーケティングの意思決定はすべて合理的になるのか?
多くのマーケターが、そんな期待とともにデータ分析を行ってきました。しかし、現実はそう単純ではありません。実際の現場では、「なぜこうなるのか?」と説明できない”非合理”な現象に日々直面しているはずです。例えば以下のようなものです。
- 無料の魔力:「”送料無料”と書くだけでコンバージョン率が跳ね上がる…」商品価格に送料を含めても総額は同じなのに、なぜユーザーの反応は劇的に変わるのでしょうか?
- 選択肢のパラドックス: 「商品ラインナップを増やしたのに購買数が減る…」論理的には選択肢が多いほど顧客満足度は高まるはずですが、現実は逆なケースも多々あります。
- 好意度と購買の乖離:「ブランド調査では高い好意度を示すのに、購買には至らない…」感情と行動が一致しない現象は、多くのマーケターを長年悩ませています。
「なぜ、緻密に設計したはずのあの施策は空振りしたのか?」「なぜ、A/Bテストで優位だったはずのクリエイティブが、本番では期待した成果を出さないのか?」こうした問いは、データと向き合うマーケターなら誰もが抱える悩みかと思います。さらに言えば、その「なぜ」を説明できないことが、再現性ある意思決定を難しくし、マーケティング部門の組織的な成長を阻害する大きな壁になっているのではないでしょうか。
顧客の行動を「可視化」する手段としてデータ分析は不可欠ですが、そこに映し出されるのはあくまで「何が起きたか」という結果にすぎません。「なぜそれが起きたのか」という背景や文脈は、データだけではわからないのです。
そこで必要になるのが、「人間はどのように意思決定するのか?」を理解する視点です。「行動経済学」は、まさにその問いに真正面から向き合ってきた分野です。本記事では、こうした「データだけでは読み解けない現象」に対し、行動経済学の視点がどのようなヒントを与えてくれるのかを、具体的な分析手法や事例とともに解説します。
目次
行動経済学が解明する「人間らしい」意思決定
人は合理的ではなく「人間らしく」判断する
従来の経済学の前提は、人は常に合理的に判断し、自分にとって最も価値の高い選択をするという「ホモ・エコノミクス」の考え方でした。ところが実際の人間は、損を避けることに敏感だったり、「人気No.1」と書かれていると安心して選ぶなど、いわば「人間らしい」けれども非合理的な判断を日々繰り返しています。
こうした現実の人間の行動パターンに注目し、それを体系的に研究するのが「行動経済学」です。ダニエル・カーネマンやリチャード・セイラーによって発展してきた行動経済学は、こうした”人間らしい判断”の法則性を数多く明らかにしてきました。
人がモノを買うとき、その決定には必ずしも「論理的な説明」があるわけではありません。「気分が良かったから」「なんとなく魅力的に感じたから」といった、言語化しづらい感情や直感に動かされることも珍しくありません。このような人間特有の心理的な傾向には、いくつかの代表例があります。
- 曖昧性効果:情報が不足しているなど、不確実性が高い選択肢を避け、より確実なものを好む
- 希少性ヒューリスティック:希少性や緊急性が行動を促進する
- 現状維持バイアス:現状から変わることに対して無意識に抵抗感が生まれる
- アンカリング効果:最初に提示された情報が後の判断に強く影響する
- 決断疲れ:選択肢が多すぎると決定を回避してしまう
- バンドワゴン効果:「他の人もそうしている」という事実が行動を後押しする
「好き」と「買う」が一致しない3つの理由
好意度が高いのに、なぜ購買には至らないのか?その理由の1つに、感情と行動が必ずしも一直線に結びついているわけではないということが考えられます。
- 時間軸のズレ:今は好きでも、買うタイミングが後になると行動しないことがあります。感情は瞬間的ですが、購買は計画的行為である場合が多いためです。
- 心理的コスト:気に入っていても、手間や不安があると購買にブレーキがかかります。「面倒な会員登録」「決済の複雑さ」「返品・交換の不安」といった心理的障壁が行動を阻害します。
- 比較効果:単体で魅力的でも、他の選択肢と比較すると劣って見えることがあります。競合商品や代替案との相対的な評価が、最終的な購買決定を左右します。
このように、「好き」や「印象」と実際の購買行動にはギャップがあります。では、このギャップをどのように理解し、分析すればよいのでしょうか?
人間らしさを読み解く行動経済学の力
ここで役立つのが、感情と行動の関係を深く探る行動経済学の視点です。データは購買という「結果」を示してくれます。しかし、本当に知りたいのは「なぜそうなったのか?」という行動の「理由」です。データだけでは説明しきれない行動の背景を、行動経済学の視点を用いることで明らかにすることが可能となります。たとえば以下のようなケースにおいて、単なるデータの背後にある人間らしい心理を理解できるようになり、マーケティングにおける仮説や解釈の精度が高められるようになります。
- 施策の効果が想定通りに出なかった:「なくなること」や「損すること」など、損失を強調する表現が心理的な抵抗を引き起こした可能性があります。
- 実質的な条件は同じでも反応が変わる:たとえ「20%OFF」と「期間限定20%OFF」、あるいは商品の提示順や「人気No.1」ラベルなど、言葉の違いや見せ方が購買意欲に大きな差を生むことがあります。
こうした行動経済学の視点は、さまざまなマーケティング分析の文脈に応用できます。つまり、データに「人間らしさ」を補うレンズとして、行動経済学は極めて有効です。
実践編:行動経済学をマーケティング分析に落とし込む
行動経済学の視点を実際のマーケティング分析に活用するためには、こうした心理的な要因を数値化し、データとして扱えるようにする工夫が必要です。この変換プロセスこそが、行動経済学とデータサイエンスを結びつける重要な要素となります。
心理的要因を数値化する4ステップ
ステップ1:抽象的な心理を具体的な行動に翻訳
まず、抽象的でわかりにくい心理的な特徴や傾向を具体的な顧客行動に変換します。たとえば、「損失を避けたい」という心理(損失回避バイアス)なら、「割引終了が近づくと購買行動に影響が出る」として、行動を観察することができます。「他の人が買っていると安心する」という心理(バンドワゴン効果)なら、「レビュー数が多い商品ほどコンバージョン率に影響が出る」などと置き換えることが可能です。
ステップ2:測定可能な変数に変換
次に、これらの行動を測定可能な数値に変換します。たとえば、以下のように分析で扱える変数として具体的に定義することができます。
- 希少性ヒューリスティック → 「在庫残数」や「数量限定」などの表示回数
- アンカリング効果 → 「定価」と「実際の購入価格」の差
- 決断疲れ → 「商品表示数」、「絞り込み機能の使用回数」
ステップ3:実データを取得
実際のデータから、先ほど定義した数値を抽出します。たとえば、Webサイトのログデータから「商品比較の行動パターン」を、購買履歴から「価格帯の推移」など、実際のユーザー行動をもとに分析に必要な材料をそろえていきます。
ステップ4:仮説を検証(例:重回帰分析)
最後に、用意した変数を使って「心理的な要因が、実際の購買行動にどう影響しているのか」を確かめます。
その方法の1つが、「重回帰分析」のような統計的なアプローチです。たとえば、「商品を表示しすぎると、かえって購買率が下がるのでは?」という仮説に対して、「商品表示数」と「購買完了率」の関係を数式で表すことで、その影響の大きさや方向性を確かめることができます。
その方程式が、こちらの「回帰式」と呼ばれるものです。回帰式は、購買率などの成果に影響を与える要因を数値的に捉えるためのモデルです。以下に、例として購買率を成果とした場合のモデル式とその意味を説明します。
購買率 = β0 + β1×商品表示数 + β2×比較行動回数 + β3×滞在時間 + ε
- β0(ベースとなる購買率):もし他の要因(商品表示数や滞在時間など)がすべてゼロだったとしても、これくらいの購買率は基本として見込めるという出発点を示す、いわば「素の状態での購買しやすさ」を表します。
- β1、β2、β3(各要因の「影響力の強さ」):それぞれの要因が、購買率をどれくらい押し上げるのか(プラスの値)、あるいは逆に押し下げてしまうのか(マイナスの値)、その「影響力の強さ」を具体的に示します。
- たとえば、β1( 商品表示数)の値がマイナスなら、「商品を表示しすぎると、かえって選ばれにくくなる」という仮説を裏付ける証拠になります。
- β3(滞在時間)の値がプラスなら、「サイトに長く滞在してくれるほど、購買につながりやすい」という関係がはっきりとわかります。
- ε(説明しきれない「誤差」):これは、モデルでは捉えきれない「人間ならではの気まぐれ」を意味します。たとえば、購入しようと思っていたのに急な電話が入った、気分が変わった、ふと別の広告が気になったなど、そうした無数の偶然が最終的な行動に影響することも少なくありません。この ε があることで、分析は決して完璧ではない、という現実的な視点を与えてくれます。
一見難しそうに感じるかもしれませんが、実は専門的な統計ソフトがなくても、Excelの「データ分析」機能で検証可能です。たとえば、Excelで得られた結果が「商品表示数の係数が-0.02」と出た場合は、「表示商品を1つ増やすごとに購買率が2ポイント下がる」ことを示します。同様に「比較行動回数の係数が-0.15」であれば、「比較回数が1回増えるごとに購買率が15ポイント下がる」ことを意味します。これにより、「商品数を20点から15点に絞り込むことで、購買率が約10%ポイント改善する可能性がある」といった、具体的な改善アクションにつながる示唆を得ることができます。
重要なのは、単なる相関(数字のつながり)を見るのではなく、その背景にある心理や行動のしくみと照らし合わせながら、解釈の妥当性を判断することです。また、この示唆は単なるUI改善に留まらず、「顧客は最適な選択よりも、後悔しない選択を求めている」というインサイトに基づき、商品戦略や売り場づくりなどマーケティング全体の考え方にまで影響を与える可能性を秘めていることもポイントです。
以下の資料で、具体的な実行方法や結果の読み解き方を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▶ 関連資料のご紹介:マーケターに力を与える、Excelでできる重回帰分析ガイド
顧客の意思決定をデザインする2つのアプローチ
ここでは、行動経済学の知見をマーケティング活動全体に活かすべく、顧客の意思決定をデザインするための2つのアプローチをご紹介します。
意味・選択・記憶の設計
行動経済学は、施策や商品・サービスの設計においても有効です。特に以下の3つの観点は、マーケターが使える「思考の型」として有用です。
- 意味の設計:顧客にとって「なぜこれが必要か?」という文脈を与えます。商品に社会的な意義や自分ごと化できる要素を与えることで、行動の理由を明確にします。たとえば、エコ商品を「地球のため」ではなく、「あなたの子どもの未来のため」というパーソナルな文脈で提示することで、購買の動機づけを強化できます。
- 選択の設計:選びやすい工夫をします。ゴールド・シルバー・ブロンズのような選択肢の数・並び順・比較対象の設計により、望ましい選択を自然に誘導できます。「おすすめ」表示や価格帯の設定も、選択の設計に含まれます。
- 記憶の設計:体験における感情のピークや終わりをどう設計するかが、ブランドの印象を左右します。会員登録後や購入後のフォロー体験で感情のピークをつくることで、長期的な関係性を構築できます。
このように、「意味・選択・記憶」の3つの設計視点を取り入れることで、行動経済学はマーケティング活動をより人間的かつ効果的なものに進化させることが可能となります。
ナッジ理論:自然な行動誘導の実践
「ナッジ」(英語:nudge)は、「そっと後押しする」といった意味を持ち、リチャード・セイラー教授(2017年にノーベル経済学賞を受賞)らによって提唱された「ナッジ理論」は、人々の自由を奪わず、しかし自然と望ましい方向に行動を促そうとする行動経済学の実践的なアプローチの1つとして知られています。マーケティングにおいては、次のようなケースで活用可能です。
- どれにしようか迷ったときに、「みんなが選んでます!」のラベルが付いていると、自然とそれを選びたくなる
- 購入ボタンを目につきやすい位置・色・大きさで配置することで、「最後の一歩」を自然に促す
- 高すぎるメニューをあえて並べることで、真ん中の価格帯が「丁度よく」見えるようにする
- 初期設定で「メール通知を受け取る」にチェックが入っていると、多くのユーザーはそのまま進んでくれる
- おにぎりやサンドイッチなどの近くに「この商品と一緒に買われています」といった表示を設置し、ドリンクやスープを配置する
- サイズや在庫に限りがある商品に「残り3点」「人気カラー完売間近」といった表示を追加する
ナッジは強制ではなく、顧客の自律的な意思決定を尊重しつつ、自然な後押しを行う手法です。これにより、顧客の人間らしい行動を踏まえた効果的なマーケティングを実現できます。ただし、過度な誘導や顧客の選択肢を実質的に狭めるような設計は、信頼を損なうリスクがあることにも注意が必要です。
まとめ:データと人間理解を両立したマーケティング
行動経済学は、感情・文脈・記憶といった、データに現れにくい要素に目を向けるための学問です。AIや高度な分析ツールが普及しても、「人はなぜそのように動いたのか」を解釈する力はマーケターに委ねられており、これからのマーケティングには、「人間らしさ」に向き合う視点がますます重要になるでしょう。
しかし、こうした顧客の複雑な心理を解き明かし、再現性のある意思決定や事業成長につなげていくには、「人間理解」だけでは不十分です。そこには、精緻なデータ分析とデータサイエンスという「科学の力」が不可欠となります。
サイカはデータサイエンスとコンサルティングを融合させ、10年以上にわたり培ってきた統計解析・モデリング技術の知見と、280社以上の企業と取り組んできた実践的な分析設計のノウハウをもとに、企業のマーケティングにおける意思決定を支援してきました。我々が大切にしているのは、データサイエンティストだけで完結する分析ではなく、マーケターの皆様が持つ市場への深い理解や顧客インサイトに裏打ちされた「仮説力」を最大限に引き出し、ともに磨き上げていく協働プロセスです。
これからのマーケティングに求められるのは、「人を理解する視点」と「データを活かす力」の両立です。サイカは、クライアントとともに仮説を深掘りし、最適な分析モデルを構築し、事業に確かなインパクトをもたらす「成長のエンジン」を実装していきます。データの力と人間理解、その両輪を回すことこそが真に顧客を動かし、”勝ち続ける”組織を実現する鍵となるのです。
▶ 関連記事のご紹介:マーケターのための仮説思考入門:実務で使いこなし、成果を出すための基本と実践