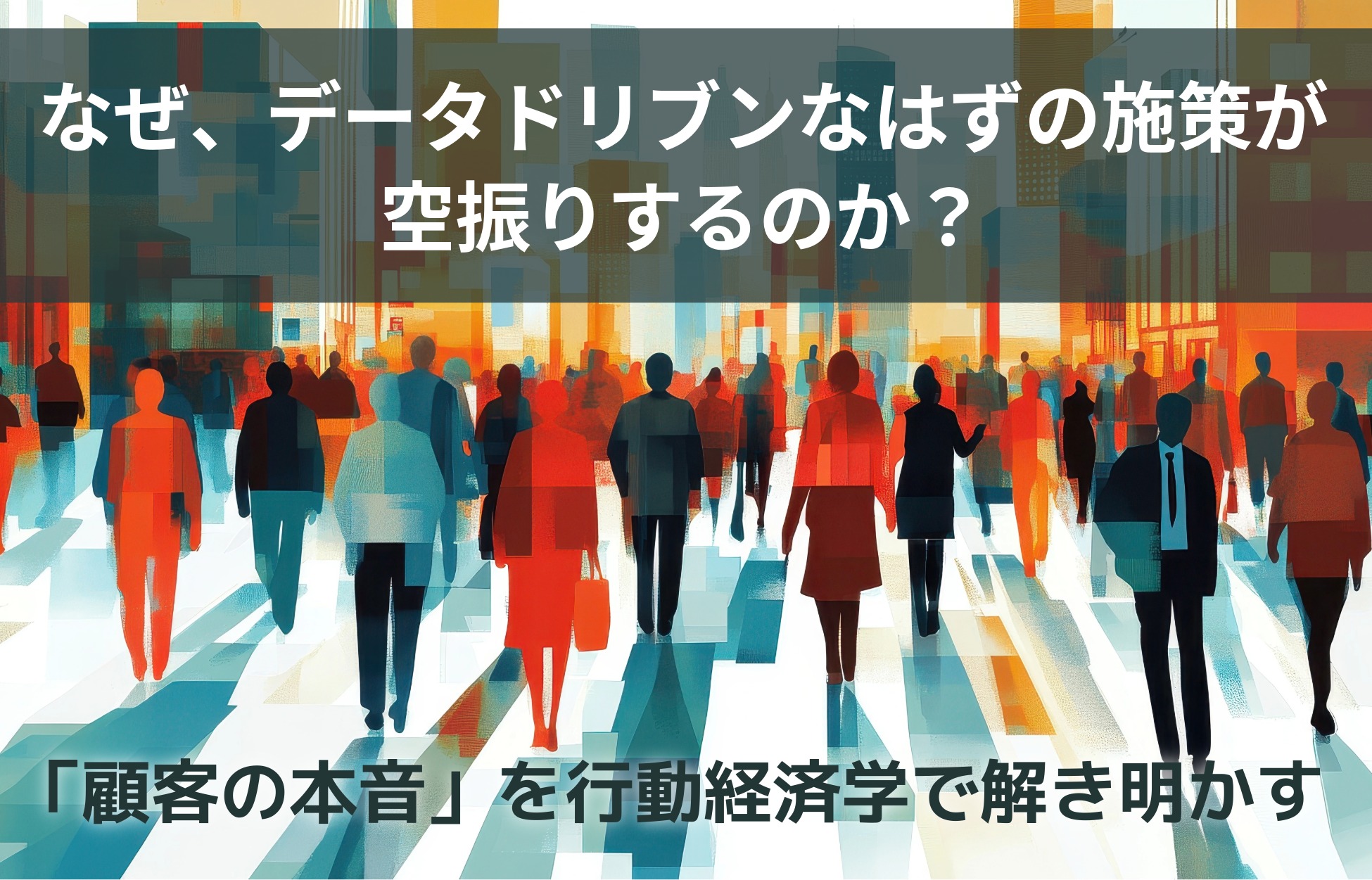データ分析の4分類とは? マーケターの問いに応える「記述的」「診断的」「予測的」「処方的」分析の役割と活用方法
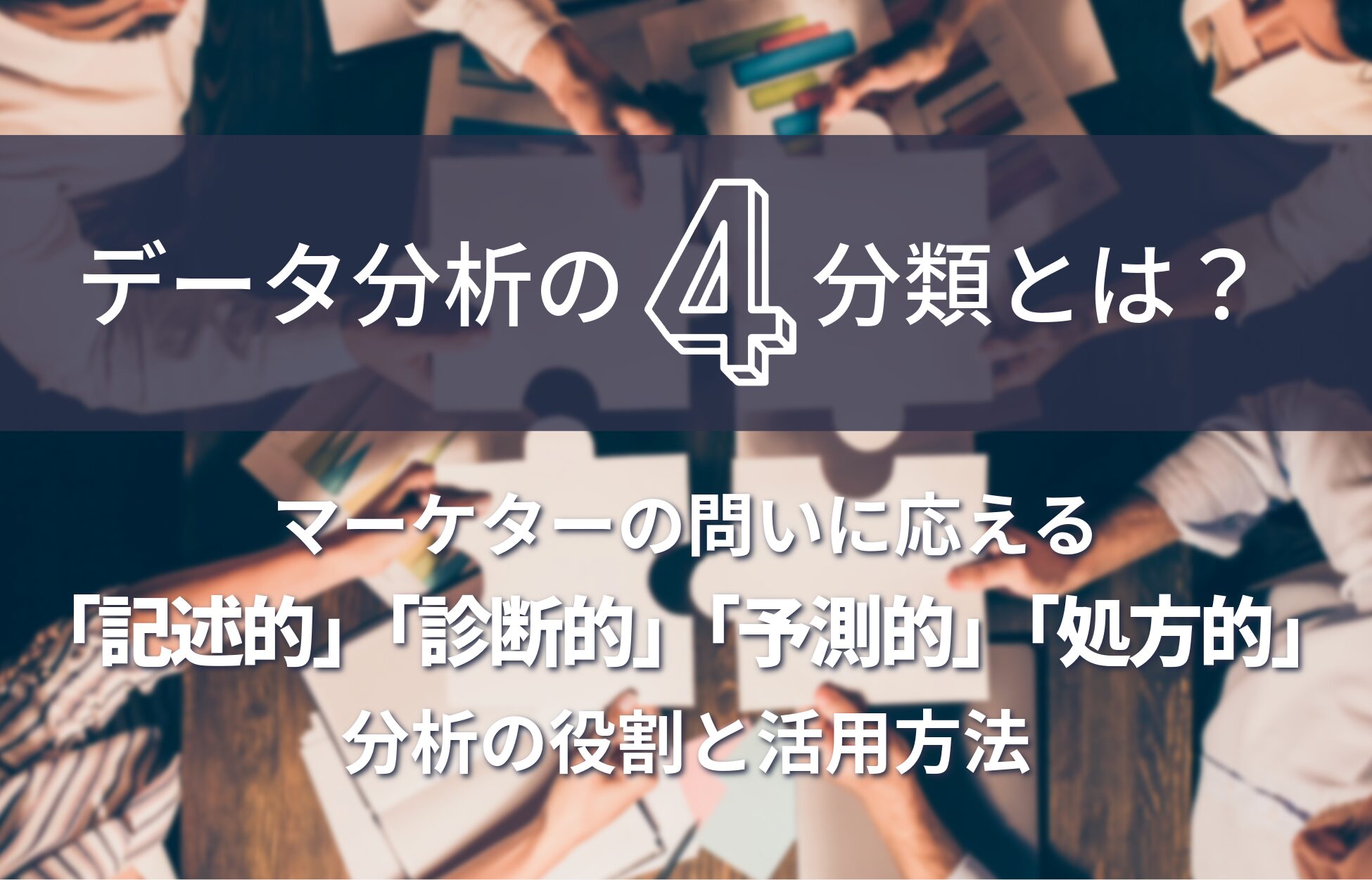
「データドリブン」という言葉が一人歩きをした結果、数字を眺めることを目的にしている現場をよく見かけます。しかし、データを見つめているだけでは、現状把握以上の価値は生まれません。本当に必要なのは、データを分析し、次の一手を導き出すことです。
さらに、ひとえに「分析」といっても原因を探ることを分析と捉えている方や、未来を予測することを分析としている方など、人によってその解釈や指している内容は様々です。
このような解釈の違いがある中で、効果的な分析、つまり何かしらの意思決定や問題解決に繋がる分析を行うには共通のフレームが必要です。そこで軸となるのが、「記述・診断・予測・処方」という4つの分析アプローチです。この記事では、マーケターとしてこの4つのアプローチの違いと使い分けを理解し、どのように活用すべきかを解説します。各分析の目的と得られるインサイトを明確にすることで、データに基づいたより精度の高い意思決定が可能となります。
目次
なぜ「データ分析の種類」を知ることが重要なのか?
意思決定は「問いの質」で決まるため
意思決定において、優れたマーケターとそうでないマーケターの違いは、データを読む技術の差ではありません。「何を問うべきか?」を見極める力、つまり「問いの質」の差です。
売上が下がったとき、「何%下がったか?」を知るのと、「なぜ売上が下がったのか?」「どのセグメントで落ち込んでいるのか?」「どの要因が影響したのか?」を探るのでは、必要な分析手法も得られる示唆も全く異なります。さらに「来月はどうなりそうか?」「どう手を打てば回復できるか?」まで考えるなら、また別のアプローチが求められるでしょう。
「どのような分析をすべきか?」を知ることが、データの活用レベルを引き上げるため
多くの企業では、データ分析の種類を意識せずに「とりあえず数字を出す・見る」というケースがよく見られますが、目的に合わない分析をいくら精緻に行っても、期待する答えは得られません。
データ分析の4つの種類を意識することで、漠然とした「データを見たい」という状態から、「何を知りたいのか?」という具体的な問いを立て、その問いに対するアプローチを整理できるようになります。たとえば、今必要なのは「今週のコンバージョン率を知りたい」という記述的な問いなのか、「先月のキャンペーンがなぜ成功したのか?」という診断的な問いなのかというものです。この問いによって、見るべきデータや適切な分析手法など、取るべきアプローチを整理することができます。
問いが明確になれば、それに適したデータ収集の方法や分析手法を迷うことなく選べるため、データ活用のレベルが向し、より的確な意思決定へとつなげることが可能になるのです。
では、マーケターが直面する多様な問いに対して、どのような分析手法が適切なのかを見ていきましょう。ここでは、データ分析を「記述的分析」「診断的分析」「予測的分析」「処方的分析」の4つに分けて、それぞれの役割と活用方法を解説します。
記述的分析:「何が起きたのか?」を捉える分析
「記述的分析(Descriptive Analytics)」は、起きた出来事や現状をデータで明らかにする分析です。すべての意思決定は、事実の把握から始まります。
活用例
売上の推移グラフ、地域別の出荷数、月次のリテンション率、ウェブサイトのアクセス解析など、現状を数字で表現し、トレンドやパターンを可視化する場面で活用されます。Google Analyticsでセッション数や直帰率を確認するのも典型的な記述的分析です。
「なるほど」で終わらせず、問いを立てる習慣を
記述的分析でよくある問題は、数字を確認して「そうか、こうなっているのか」で終わってしまうことです。しかし、データが示す事実に「意味づけ」をしなければ、データの価値を活かし切れません。たとえば「新規顧客獲得数が前月比80%」という事実があったとき、これを「下がっている」で終わらせるのではなく、「季節要因なのか、競合要因なのか、それとも自社施策の影響なのか?」という次の問いを立てることが大切です。
週次レポートやダッシュボードで数字を眺めるときも、「次に調べるべきことは?」「どんな仮説が考えられるか?」という視点を持つことが必要です。記述で終わらず、問いへとつなぐことで、分析の意味が生まれます。
・関連記事のご紹介:マーケターのための仮説思考入門:実務で使いこなし、成果を出すための基本と実践
診断的分析:「なぜ起きたのか?」を解き明かす分析
「診断的分析(Diagnostic Analytics)」は、記述的分析で明らかになった現象の原因を探る分析です。「なぜその結果になったのか?」を深掘りすることで、問題の構造や要因を把握します。
活用例
CVRが急に下がった原因を探るとき、広告施策の効果差を比較するとき、特定地域で売上が伸びない理由を検証するときなどに活用されます。セグメント別分析、A/Bテストの結果解釈、コホート分析(ユーザーをグループ化し、そのグループごとの行動を分析する)などが代表的な手法です。
「相関」ではなく「因果」を探る視点
診断的分析でもっとも重要なのは、相関関係と因果関係を混同しないことです。「雨の日は売上が下がる」という相関があっても、「雨が売上を下げている」とは限りません。雨の日は外出を控える人が多いから、という因果関係が隠れているかもしれません。マーケティングの現場では、この区別があいまいになりがちです。「広告費を増やした月は売上も上がった」という相関を見て、「広告費が売上を押し上げた」と結論づけてしまう前に、他の要因も検討する必要があります。
思い込みを疑う視点
診断的分析には思い込みを疑う視点が必要です。「たぶんこれが原因だろう」と決めつけず、複数の仮説を立て、データで検証する姿勢が意思決定の質を大きく左右します。原因の特定を間違えると、的外れな対策を打つことになり、時間とリソースを無駄にしてしまいます。
・関連記事のご紹介:マーケティングにおける因果推論の基本と重要性
予測的分析: 「このままだとどうなるのか?」を見通す分析
「予測的分析(Predictive Analytics)」は、過去と現在のデータをもとに、未来に起こり得ることを推測する分析です。傾向やパターンをもとに、次に起きることを見通します。
活用例
来月の売上予測、顧客の離反リスク判定、新商品の反応シミュレーション、LTV(顧客生涯価値)の予測など、マーケティングの多くの場面で活用されています。レコメンドやパーソナライズ施策、チャネルごとの予算配分にも応用されており、これらは次の「処方的分析」の領域にもまたがります。
未来は「当てる」ものではなく、「備える」もの
予測的分析に対してよくある誤解は、未来を当ててくれる絶対的なもののように期待してしまうことです。しかし実際には、予測モデルは「現在の傾向が続いた場合の可能性」を示すものであり、絶対的な未来を保証するものではありません。予測はナビのようなものです。完全な地図ではなく、「このまま進むと渋滞が起こりそう」「こちらの道ならスムーズかも」といった道しるべとなる存在です。
予測モデルの前提を理解する
予測的分析を使う際には、「モデルがどのような前提に基づいているか」を理解する必要があります。予測モデルは過去のデータや特定期間の傾向に基づくため、環境変化には弱いという限界があります。たとえば、コロナ禍以前のデータで学習したモデルは、パンデミック中の予測には適しません。前提を理解し、柔軟に運用することが、予測モデルを意思決定に活かす鍵となります。
・関連記事のご紹介:環境変化を味方に:市場で勝ち抜くマーケティング戦略
処方的分析:「どうすればより良くなるのか?」を導く分析
「処方的分析(Prescriptive Analytics)」は、予測結果をもとに最適な行動を導き出す分析です。未来を「当てる」から「変える」へとつなげるステップです。
活用例
「来期のマーケティング予算を各チャネルにどう配分すれば、売上を最大化できるか?」この問いに答えるのが処方的分析の典型例です。MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)による予算最適化シミュレーション、価格の動的調整、顧客セグメント別に施策効果を最大化するためのアプローチ最適化などが代表的です。
「常に正解を出してくれる」わけではない
処方的分析に対する大きな誤解は、それが自動的に最善策を出してくれる魔法の杖だと思ってしまうことです。実際には、ビジネス目標の設定、制約条件の定義、優先順位の決定など、人の判断が不可欠な要素が数多くあります。
分析結果や示唆の前提を確認する
分析結果や示唆に対し「どのような前提で出された示唆か?」「その前提は現実に合っているか?」という視点を持つことが重要です。処方的分析は人の判断を代替するものではなく、より良い意思決定を支援する材料です。データと人の判断を組み合わせることで、よりよい打ち手が見えてきます。
・関連記事のご紹介:MMMとは?特徴、手順や事例などを解説
分析の種類を“問い”で選ぶ、実務で迷わないための整理
ここまで4つの分析を個別に説明してきましたが、実際のマーケティングでは、これらを連続的に使い分けることが重要です。
また、同じデータを使っても、立てる問いによって必要な分析は変わります。「売上が下がった」という事実に対して、「どのくらい下がったか?」(記述)、「なぜ下がったか?」(診断)、「このまま下がり続けるか?」(予測)、「どう対処すべきか?」(処方)では、全く異なるアプローチが求められます。
優秀なマーケターは、この使い分けを直感的に行えているかもしれませんが、データ分析の4分類を意識することで、この直感を言語化できるようになります。そうすることで、チーム内や組織全体でも共通の理解が生まれ、より一貫性のあるデータ活用が可能になります。
よくあるマーケティングの課題と、それに適した分析の種類
| よくある問い | 対応する分析の種類 | 主な目的・活用シーン |
| 先月の実績はどうだったのか? | 記述的分析 | KGIやKPIなどの主要指標を整理し、事実ベースで「何が起こったか」を把握・共有する |
| この施策は効果があったのか? | 診断的分析 | 変化の要因を深掘りし、施策が成果にどう寄与したかを明らかにする |
| 次の四半期の売上はどうなるか? | 予測的分析 | 現在のトレンドや外部環境をもとに、将来の成果をシミュレーションし、中期的な計画に活かす |
| どこに、いくら投資するべきか? | 処方的分析 | 費用対効果やシミュレーションを通じて、限られた予算を最適に配分するための判断材料とする |
本記事では分析の4つの種類について解説していますが、実務においては「具体的にどの手法(重回帰分析、MMM、決定木など)を使えばいいのか?」という選定で悩むことも多いでしょう。
以下の記事では、代表的な13の分析手法をビジネス課題別に整理し、成果を出すための選び方を解説しています。具体的な手法の選定に進みたい方は、ぜひ併せてご覧ください。
・関連記事:マーケティングデータ分析の正攻法|成果向上に欠かせない13の手法と選び方
各分析の成果を関係者に効果的に伝える方法
分析が結果を関係者に正しく伝え、意思決定につなげられなければ、分析の価値を最大限に引き出すことはできません。各分析には、それぞれに最適なコミュニケーション方法があります。
記述的分析の伝え方:「事実を共有し、次の問いを誘発する」
記述的分析の結果を伝える際、多くの人が陥りがちなのは、「数字を並べて終わり」にしてしまうことです。しかし、関係者が求めているのは数字そのものではなく、重要なのが「その数字が何を示唆しているか」です。
伝え方の工夫:
- 「売上が前月比○○%でした」ではなく、「売上が前月比○○%となり、過去6ヶ月で最も低い水準になりました」のように、重要な変化点を説明する
- 「この変化の要因を明らかにするため、次に△△の傾向を確認したいと考えています」と、数字に文脈を与え、次のアクション(=診断的分析)へとつなげる
診断的分析の伝え方:「仮説と検証のプロセスを明確にする」
診断的分析では、「なぜその結論に至ったのか」という論理的な道筋を示すことが重要です。関係者は結論の妥当性を判断し、納得して意思決定するために、分析の前提や制約、検証の過程を理解する必要があります。
伝え方の工夫:
- 「3つの仮説を立て、それぞれに対して直近3ヶ月のデータを分析しました。その結果、最も大きく影響していたのは○○要因と判明しました。ただし、○○と売上には相関がありますが、因果関係までは特定できていません」のように、仮説や検証プロセスを明示しつつ、相関と因果を区別して説明
- 「この分析では△△が変化しないことを前提にしています。また、□□の影響は除外していますが、無視できない可能性もあります」と、前提や制約を明確にする
予測的分析の伝え方:「不確実性を含めて、意思決定に必要な情報を提供する」
予測的分析の結果を伝える際に最も重要なのは、「確実であるかのような錯覚を与えない」ことです。予測はあくまで未来への見通しであり、必ず不確実性を含むものです。
伝え方の工夫:
- 「現在のトレンドが続けば、来月は○○の可能性が高く、±△%の幅で推移する見込みです」のように、予測の前提条件や不確実性の幅を示す
- 「ただし、□□の要因が変われば、予測は変わります」と、前提条件が変われば結果も変動することを明示する
処方的分析の伝え方:「選択肢とその特徴を整理し、判断材料を提供する」
処方的分析では、「これが最適解です」と断言するのではなく、複数の選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを提示することで、「決めてもらうための土台」をつくることが重要です。
伝え方の工夫:
- 「3つの選択肢を検討しました。A案は○○、B案は△△、C案は□□です」と、選択肢を整理する
- 「コスト重視ならA案、スピード重視ならB案が適しています」のように、判断軸を示す
関係者別のコミュニケーション調整
データ分析の結果を共有する際は、相手の立場や関心に応じて伝え方を変えることも重要です。
たとえば、現場担当者には具体的なアクションに結びつく情報を伝える必要があります。「○○キャンペーンの△△要素が効果的でした。□□の施策で活用可能です」(診断的分析)、「○○を△△に変更することで、□□の改善が期待できます」(処方的分析)のように、施策や次のアクションにつながる情報を提示することが重要です。
一方、経営層にはビジネス全体へのインパクトを端的かつ定量的に伝えることが求められます。「売上が前年同期比で○○%下落し、その結果、昨年と比較して△△億円の損失になりました」(記述的分析)、「○○要因に対する対策をしない場合、6ヶ月後に△△のリスクがあります」(予測的分析)など、意思決定に直結する要点を簡潔に示しましょう。
実務でよくある「分析あるある」とその対策
これまでの内容を理解できても、データ分析を日常業務に取り入れる過程で直面する典型的な課題もあります。
あるある①:「分析しろ」と言われてやるが、何を見ればいいかわからない
「とりあえず分析して」と指示されたものの、どの指標を見るべきか、何から手をつけていいかわからない状況です。これは、“問い”がないままに分析を始めてしまった際に起こる典型例です。問いが曖昧なままでは、どれだけ時間をかけてデータを集め、分析しても、有益な洞察は得られません。
対策:まず「何を判断したいのか?」「そのために何を知る必要があるのか?」を明確にすることから始めましょう。問いが明確になれば、必要な指標・分析手法・データや集計粒度なども自然と定まります。逆に言えば、「問いが曖昧なまま始まる分析」は、ほぼ確実に眺めるだけのレポート止まりになります。
あるある②:ダッシュボードはある。でも、誰も意思決定に使っていない
美しいダッシュボードを作ったものの、日常的に見られていない、あるいは見ても何も変わらないケースは意外と多いものです。背景には、「誰が」「いつ」「何のために」見るべきかが設計段階で不明確だったことがあります。また、表示されている数字が行動につながる問いになっていないこともあります。
対策:ダッシュボードを作る際には、「この指標の変化を誰がチェックし、それによってどんな判断・行動を取るのか?」を明確にしておきましょう。単なる記述的な数値の羅列ではなく、そこから診断 → 予測 → 処方的判断へとつなげる流れが組み込まれていることが理想です。
あるある③:「数字はわかったけど、結局どう動けばいいの?」で止まる
分析結果は出たものの、それをアクションに落とし込めないケースです。「CVRが下がっている」という事実がわかっても、「だからどこを改善すればいいのか?」「何を試すべきなのか?」といった次の一手に結びつかないまま、レポートで止まってしまうのです。
対策:分析結果に対しては、必ず「So what?(だから何?)」と「What’s next?(次に何をする?)」の問いを投げかけるクセをつけましょう。数字の把握で終わらず、必ずアクション提案まで含めることが重要です。たとえば、「CVRが下がった」なら、「クリエイティブが原因なのか?」「流入経路の変化か?」といった仮説を立て、次にそれを検証するための取るべきA/Bテストやメッセージ改善など、具体的なアクションまで考えることが重要です。
あるある④:分析結果を意味ある行動に変換できる人がいない
「アクションに落とせない」もう一つの大きな理由は、分析とビジネスを橋渡しできる人材の不在です。
記述 → 診断 → 予測 → 処方といった分析の流れをビジネス成果につなげるには、「データの意味」と「現場の判断」をつなぐ“翻訳者”が欠かせません。たとえば、データサイエンティストは分析のプロですが、ビジネス現場での情報や優先順位づけにおいては専門外であることもあります。一方、マーケターはビジネス感覚はあるものの、分析手法の理解や解釈に課題を抱えていることがあります。
対策:この翻訳者的な役割は、必ずしも専任の職種である必要はありません。社内にいる分析リテラシーの高いマーケターや、事業理解のあるアナリストでも構いません。あるいは、外部のパートナーやコンサルタントを活用することも有効です。
また、もしデータサイエンティストと協働することになった際には、お互いの専門性を尊重しつつ、共通の言語で対話することが重要です。たとえば、「来期の売上予測をお願いします」という依頼よりも、「来四半期の売上を予測的分析で見通しを立て、処方的分析で実行施策を導き出したい。直近で売上が鈍化してきており、要因としては既存顧客の離脱増加や再訪率の低下が影響しているのでは、という仮説がある。そのため、リピート率やLTVに関する指標も含めて分析してほしい」といった依頼のほうが、データサイエンティストがやるべきこと、マーケターが期待しているアウトプットが明確になり、より建設的なコミュニケーションにつながります。なお、仮説が間違っていても問題はありません。むしろ仮説があることで、分析の出発点が明確になり、分析者との対話の精度が上がるのです。
マーケターに必要なのは「すべてを理解すること」よりも、「問いを立て、活用する力」
ここまで、4つの分析アプローチについて詳しく紹介してきましたが、マーケターにとって最も重要なのは、ビジネス課題を「問い」に変換する力です。「売上を上げたい」「離脱を減らしたい」「顧客満足度を上げたい」といった漠然とした課題を、「どのセグメントの、どの商品の売上を、いつまでに、どのくらい上げたいのか?」「何を改善したいのか?」という具体的な問いに変換できるかどうかが、成功の第一歩です。
また、すべてのマーケターが高度な分析スキルを身につける必要はありません。たとえば、料理人は農業や漁業の専門知識がなくても、素材の特徴を理解し、優れた料理を作ることができます。同じように、マーケターも「分析の使い方」さえ理解していれば十分に戦えます。大切なのは、分析結果の意味を理解し、どう意思決定に活かすかを考える視点を持つことです。
おわりに
この記事を読み終えた今、ぜひご自身のチームを振り返ってみてください。今、どんな問いを立て、どのような分析を行っていますか?
もし、「とりあえずデータを見ている」「レポートが溜まっているだけ」と感じるなら、まずは問いを再設計することから始めましょう。すでに明確な問いがあるなら、その問いにもっとも適した分析手法を選べているか、今一度見直してみてください。分析は、問いと手法の相性が合ってはじめて価値を生みます。本記事が、皆さまの問いをより一層深め、データ活用を成果に結びつけるきっかけになれば幸いです。
「もっと戦略的にデータを使いたい」「分析はしているけれど、次の打ち手につながらない」、そんなお悩みがあれば、ぜひ一度サイカまでご相談ください。
サイカは、10年以上にわたって累計300社以上の企業とともに、マーケティングの意思決定を支える分析に取り組んできました。MMMをはじめとする高度な手法・テータサイエンスを駆使し、複雑な環境下でも実行できる打ち手を導き出します。
我々の支援は、単なる分析の提供にとどまりません。「そもそも何を問うべきか?」というビジネス課題の整理から始まり、分析をどう判断に組み込み、どう組織に根づかせるかまでを、一気通貫で伴走します。私たちは、“使える分析”を通じて、クライアントの意思決定力を高め、ビジネス成果に直結する支援を行っています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 4つの分析は、必ず順番通りに進めないといけませんか?
いいえ、必ずしも順番通りである必要はありません。ビジネスの状況や課題によって、どこから始めるかは変わります。
記述から始まるケース(最も一般的)
- 定期レポートやダッシュボードで現状を把握
- 異変に気づいたら診断的分析へ
- トレンドが見えたら予測的分析へ
診断から始まるケース
- すでに問題が明確な場合(「CVRが急落した」など)
- 原因究明が最優先
予測から始まるケース
- 予算策定や計画立案の時期
- 「来期どうなるか?」が先に知りたい場合
ただし、処方的分析は診断や予測の結果がないと実行できないため、多くの場合は他の分析を経てから行います。
Q2. 「分析しろ」と指示されたが、何から手をつければいいかわからない
まず、「何を判断したいのか?」「そのために何を知る必要があるのか?」を明確にすることから始めましょう。
具体的なステップ
- ゴールを確認する:この分析で何を決めたいのか?(予算配分、施策の継続/中止、新規施策の立案など)
- 問いに変換する:「売上を上げたい」→「どのセグメントの売上を、いつまでに、どのくらい上げたいのか?」
- 分析の種類を特定する:
- 現状把握が必要 → 記述的分析
- 原因を知りたい → 診断的分析
- 将来を見通したい → 予測的分析
- 打ち手を決めたい → 処方的分析
- 必要なデータを確認する:その問いに答えるために、どんなデータが必要か?
問いが明確になれば、必要な指標、分析手法、データの粒度も自然と定まります。逆に、問いが曖昧なままでは、どれだけ時間をかけても「眺めるだけのレポート」で終わります。
Q3. ダッシュボードを作ったのに、誰も使ってくれない
これは非常によくある課題です。原因の多くは、「誰が」「いつ」「何のために」見るべきかが不明確だったことにあります。
見直すべきポイント
- 使う人を特定する:経営層?現場マネージャー?実務担当者?
- 見るタイミングを決める:週次ミーティング前?月次レビュー時?異常値アラート時?
- 行動につなげる設計:この指標が変化したら、誰が何をするのか?
改善のヒント
単なる数値の羅列ではなく、そこから診断→予測→処方的判断へとつなげる流れを組み込みましょう。たとえば、「CVRが先週比で15%下落」(記述)という表示だけでなく、「主要なランディングページのCVRが下落。流入経路の変化が影響している可能性」(診断的な示唆)まで含めると、見る人が次のアクションをイメージしやすくなります。
Q4. 分析結果は出たが、結局どう動けばいいかわからない
これは、分析が「記述」や「診断」で止まっていて、「処方」まで到達していないケースです。
対策
分析結果に対して、必ず以下の2つの問いを投げかけるクセをつけましょう。
- 「So what?(だから何?)」:この結果が示す意味は?
- 「What’s next?(次に何をする?)」:具体的に何をすべき?
具体例
- ✕「CVRが下がった」で終わる
- 〇「CVRが下がった」→「クリエイティブが原因か?流入経路の変化か?」(仮説)→「A/Bテストで検証する」または「流入経路別に分析する」(次のアクション)
数字の把握で終わらず、必ずアクション提案まで含めることが重要です。
Q5. データサイエンティストとうまく協働するコツは?
お互いの専門性を尊重しつつ、共通の言語で対話することが重要です。
- ✕ 曖昧な依頼 :「来期の売上予測をお願いします」
- 〇 明確な依頼 :「来四半期の売上を予測的分析で見通しを立て、処方的分析で実行施策を導き出したい。直近で売上が鈍化してきており、要因としては既存顧客の離脱増加や再訪率の低下が影響しているのでは、という仮説がある。そのため、リピート率やLTVに関する指標も含めて分析してほしい」
ポイント
- 何を知りたいか(目的)を明確にする
- なぜ知りたいか(ビジネス背景)を共有する
- 仮説があれば伝える(間違っていても問題ない。むしろ分析の出発点が明確になる)
- どう使うか(意思決定への活用方法)を伝える
仮説が間違っていても大丈夫です。むしろ仮説があることで、分析の出発点が明確になり、対話の精度が上がります。
Q6. 相関と因果の違いを、実務でどう意識すればいいですか?
「一緒に動いているだけ」(相関)と「原因と結果」(因果)を混同しないことが重要です。
よくある誤解の例
- 「広告費を増やした月は売上も上がった」→だから広告費が売上を押し上げた
- 「雨の日は売上が下がる」→だから雨が売上を下げている
実務での確認方法
- 他の要因を検討する:同時期に他に何か変化はなかったか?
- 時間の前後関係を確認する:原因が結果より先に起きているか?
- 複数のデータで検証する:別の期間やセグメントでも同じ関係が見られるか?
- 実験的に確認する:A/Bテストなどで、意図的に条件を変えて検証できないか?
完全な因果関係の証明は難しいですが、「これは相関かもしれない」という疑いを持つだけでも、的外れな判断を防げます。
Q7. 予測モデルの精度が低い場合、使う意味はありますか?
はい、あります。予測の目的は「未来を完璧に当てること」ではなく、「より良い意思決定をすること」だからです。
予測の価値
- 精度60%の予測でも、勘だけよりは確実に判断の質が上がる
- 「このままだと危ない」という早期警告になる
- 複数のシナリオを比較できる(「A案なら○○、B案なら△△の可能性」)
重要なのは
- 予測の不確実性を理解した上で使う
- 予測結果を絶対視せず、他の情報と組み合わせる
- 定期的に精度を検証し、改善を続ける
予測はナビのようなものです。完全な地図ではありませんが、「このまま進むと渋滞が起こりそう」という道しるべとして十分に価値があります。
Q8. 経営層に分析結果を説明する際のコツは?
経営層には、ビジネス全体へのインパクトを端的かつ定量的に伝えることが求められます。
✕ 避けるべき説明
- 専門用語の羅列(「決定係数が0.8で、p値が0.05未満でした」)
- 分析手法の詳細説明(「重回帰分析を用いて…」)
- 結論のない数字の報告(「売上が下がりました」で終わる)
〇 効果的な説明
- 結論を先に言う:「○○の対策を実施すれば、△△億円の改善が見込めます」
- ビジネスインパクトを金額で示す:「売上が前年同期比で15%下落し、その結果、昨年と比較して3億円の損失になりました」
- 選択肢と判断軸を提示する:「A案はコスト重視、B案はスピード重視です。リスクは○○です」
- 次のアクションを明確にする:「まず○○を実施し、2週間後に効果を検証します」
- 不確実性も正直に伝える:「○○要因に対する対策をしない場合、6ヶ月後に△△のリスクがあります」
経営層が求めているのは分析の詳細ではなく、「それで、どうすればいいのか?」という判断材料です。