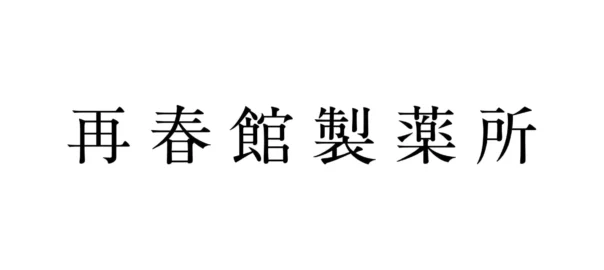Q. Oisix様には、2018年の冬にMAGELLAN(マゼラン)をご導入いただきました。当時、どのようなマーケティング課題があったのでしょうか?

西井様:Oisixでは、現在約20万人の会員数を、3年間で50万人に成長させるという事業計画を立てています。しかし、プロモーションのファネルをOisixに対する顕在層から潜在層へと広げると、CPAが高くなってしまう傾向がありました。そこで、ラストコンバージョンではなく、Webのアトリビューション分析を行ったのですが、Oisixへのアクセスは、8割がスマートフォンからです。現状、デバイスを超えたアトリビューション分析は難しく、またオフライン活動の影響も可視化はできません。
このように、プロモーション全体の効果測定は長らくの課題です。しかし、認知と獲得の両方を実現するためには、最適なメディアを判断し、投資するためのファクトを掴まねばなりません。現在も、MAGELLANを含めて、プロモーション全体の効果分析を進めているところです。
CPAはトータルで考える
Q. MAGELLANを導入された理由を教えて下さい

成宮様:MAGELLANを導入した当時に私が所属していたOisixEC事業本部プロモーション室は、「おいしっくすくらぶ」の新規会員獲得がミッションです。デジタル広告は詳細な分析が進んでいますが、テレビCMなどのマス広告に関しては、効果指標や同時期に走らせるキャンペーンの設計を、経験則で行ってきた状況があります。MAGELLANはマス広告の効果も可視化できますから、ファクトに基づいたアロケーションに期待して導入しました。

藤枝様:EC事業本部のデータマーケティングセクションでは、サービスに紐づいたデータの蓄積、可視化、活用を行っています。Oisixの事業が伸びている理由の1つに、会員の獲得コストとLTVの一致があります。ゆえに、プロモーション全体の効果測定は、常に最善を追い求めなければなりません。また、広告予算のアロケーションに、統計学的なアプローチを取り入れられないかと考えていました。そのような中でMAGELLANをセミナーで知り、「Oisixの構想が実現できそうだ」と感じたのです。
Q. 近年、ダイレクトレスポンス型のビジネス全般に、CPA評価が難しくなってきた傾向があると伺います。Oisix様では、CPAをどのように捉えていらっしゃいますか?
西井様:ラストクリックの成果だけでなく、マス広告や動画広告も含めてPDCAを回し、トータルでCPAが合えば良いと考えています。そこへ、多角的な視点として統計のアプローチも交えていけるのではないでしょうか。デジタルマーケティングが登場する以前は、広告効果が十分に可視化されず、感覚的なアロケーションをせざるを得ませんでした。しかし、このブラックボックスの状態を明らかにし、正しいマーケティング投資ができれば、企業は伸びると思います。
お客様の行動を深く理解し、最適な広告手法を選択したい
Q. 最後に、マーケティングにおいて目指す姿について教えて下さい
藤枝様:Oisixでは週次でPDCAを回しており、スピードを大切にしています。現在は、データマーケティングセクションがサポートしながら、MAGELLANの分析設計を構築している段階です。よりスピーディに分析が行えるよう、マーケターが1人でMAGELLANを運用できる体制を整えたいです。
成宮様:運用型広告のプラットフォームは、広告配信システムの学習機能が進化し、クリエイティブの力で効果を上げていく傾向があります。広告を起点としたお客様の行動を可視化し、その上でクリエイティブの評価も可視化できると理想的ですね。ファクトに沿って、最適なマーケティングコミュニケーションを実現したいと思います。
西井様:今や「ダイレクトレスポンスは運用型広告」が当たり前となりましたが、10年ほど前は、ディスプレイ広告を活用しきれていなかった時代もあります。しかし、プラットフォーム側のテクノロジーの進化に伴い、CPAが合うようになり、広告投資が進みました。今後も同様に、動画広告などの新しい広告が定着し、クリックベースではない計測指標や手法が確立する時が来るでしょう。そのようなマーケティングの変化にしっかりと対応できるよう、準備を進めておきたいです。