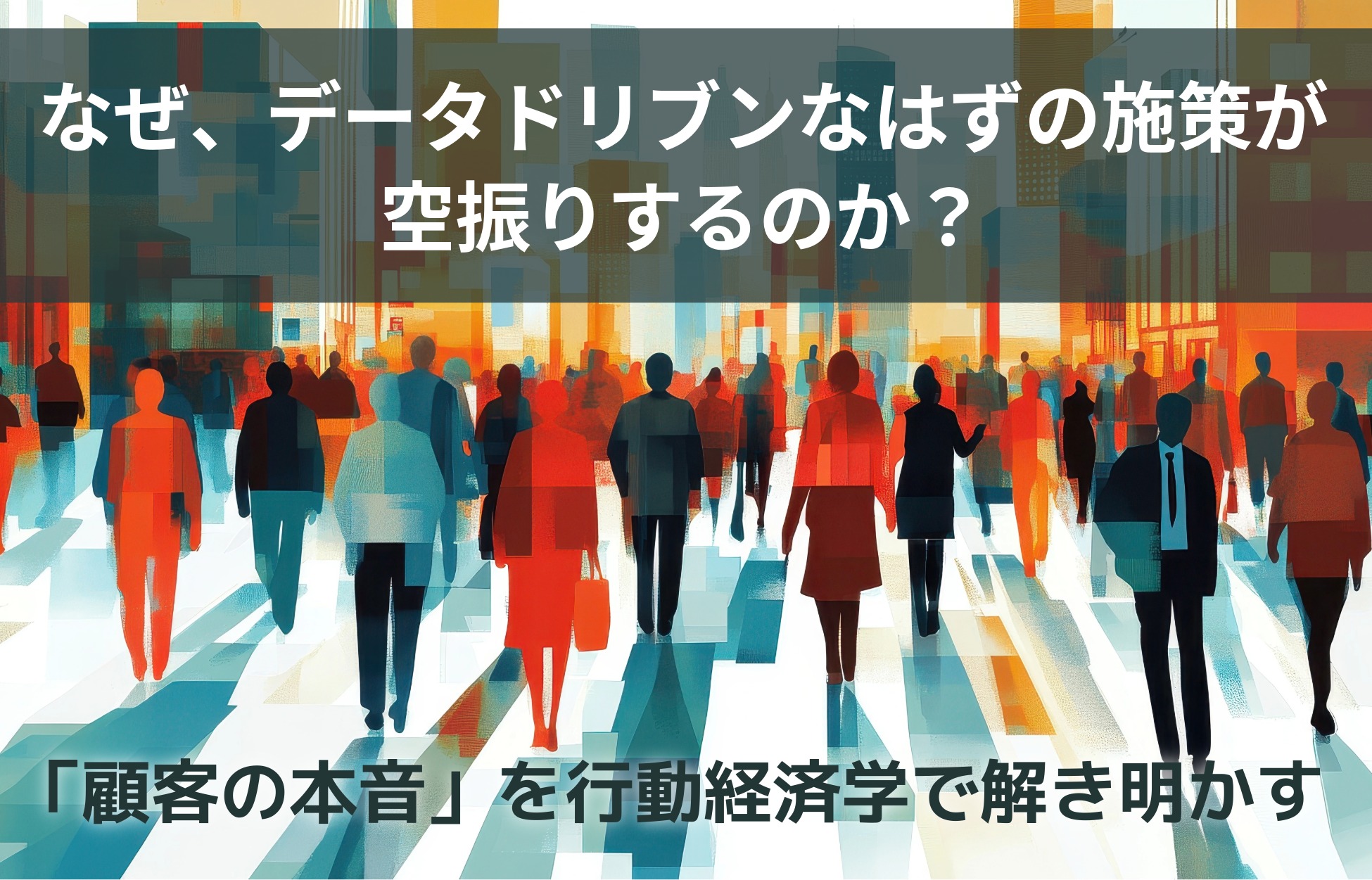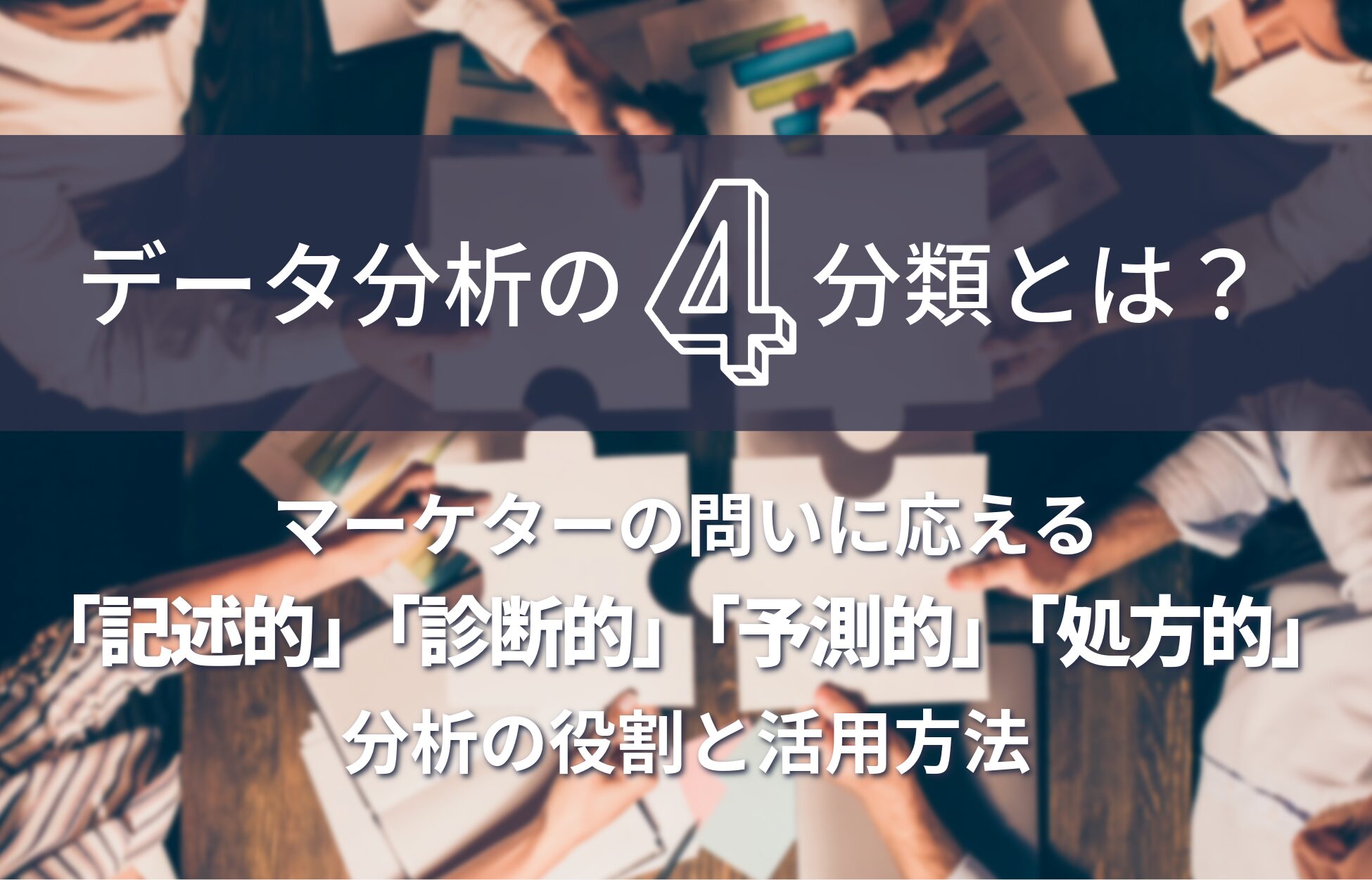マーケティングでの統計モデル一覧:概要、活用法、課題と要件を分かりやすく解説(方程式なし)

統計分析は、現代のビジネス環境で不可欠な手段となっています。企業はますますデータドリブンな意思決定を求めるようになっていますが、その成功の鍵となるのが統計モデルです。
「自社で統計モデルが活用されているが、実は良くわらない」「より効果的なマーケティングの実践に向けてこれから取り入れたい」と考えている方々へ、本記事では主な統計的モデリング手法の概要、活用事例、そして課題と前提条件などをわかりやすく解説していきます。
目次
- 統計モデルとは?
- マーケティングでの活用シーン
- 統計モデルを使う3つのメリット
- マーケティングで使える統計モデル8選
- 終わりに
統計モデルとは?
統計モデルとは、データからパターンや関係性を見つけ出し、それを数式で表現する手法です。「原因となる要素(説明変数)」と「結果(目的変数)」の関係を数値で捉えることで、予測や意思決定に役立てられます。
身近な例は天気予報です。気圧、湿度、気温、風速といった要素から、いつ、どこで、どれくらい雨が降るかを予測しています。これがまさに統計モデルの働きです。
マーケティングでの活用シーン
統計モデルは、マーケティングのさまざまな場面で力を発揮します。
- 市場セグメンテーション:顧客をどうグループ分けするか
- 顧客の行動予測:誰が、いつ、何を買うのか
- 広告・プロモーションの最適化:どの施策が効果的か
統計モデルを使う3つのメリット
1. 透明性と説明力
統計モデルは、マーケティングの結果を科学的に説明できます。「なぜこの結果になったのか」「どの要素が影響したのか」が明確になるため、上司やチームメンバー、他部門への説得力が増します。
2. 精度の高い予測
商品の需要や売上を正確に予測することで、予算配分や在庫管理、生産計画を最適化できます。結果として、コスト削減と効率向上を実現できます。
3. 意思決定のサポート
経営層やマーケティング責任者は、分析結果を基に戦略を立てられます。勘や経験だけでなく、データに裏打ちされた判断ができるようになります。
マーケティングで使える統計モデル8選
1. 重回帰分析(Multiple Regression Analysis)

重回帰分析の概要
重回帰分析は、何かの出来事や結果が複数の要因によって影響を受ける場合、それらの要因と結果の関係を理解するための手法です。この分析を通じて、結果にどの要因がどの程度影響を与えているかを評価し、要因間の関係性を明らかにします。この手法の目的は、要因と結果の関係を数学的にモデル化し、因果関係を理解することです。重回帰分析では、結果(目的変数)と複数の要因(説明変数)との関係性を式で表現します。これにより、異なる要因が結果に対してどの程度影響を与えるかを推定できます。モデルは数学的な式として表現され、要因と結果の関係を示す係数が計算されます。これにより、要因の影響度や因果関係を明らかにします。
活用例:広告効果の分析
広告効果の分析として、広告費、ソーシャルメディアの投稿、季節要因などを説明変数として使用し、売上や顧客の獲得などの成果を目的変数として重回帰分析を実行することができます。これにより、どの広告チャネルや要因が成果に最も影響を与えているかを理解し、効果的な広告戦略を立てるのに役立ちます。
重回帰分析における課題
主な課題には、多重共線性(予測変数間の相関が高い)、オーバーフィット/過剰適合(モデルが複雑すぎる)、アンダーフィット/過小適合(モデルが単純すぎる)などがあります。また、重回帰分析は予測変数と結果の間に線形な関係(予測変数の変化に合わせて、結果が変化する割合が常に一定であること)を仮定した分析モデルになりますが、これは現実に常に保持される現象とは限りません。
重回帰分析が有効となる条件
多重共線性が低く、複数の要因間の線形関係における仮説を検証したい時には重回帰分析が有効です。
2. 階層的重回帰分析(Hierarchical Multiple Regression Analysis)

階層的重回帰分析の概要
階層的重回帰分析は、結果に対する影響を調べる方法で、さまざまな要因を段階的に評価する手法です。この分析の目的は、結果への影響を理解し、どの要因が最も影響力を持つかを特定することです。この手法は、結果に寄与する主要因とその相対的な重要性を評価するのに役立ちます。階層的重回帰分析は、まず最も基本的な要因を評価し、その後、他の要因を順次追加して影響を評価します。モデルの構築段階で、要因間の因果関係や相互関係を仮定し、それらの影響を統計的に分析します。
活用例:価格設定の最適化
商品の価格を説明変数として扱い、売上を目的変数として階層的重回帰分析を実行することで、最適な価格を分析することができます。基本的な要因を商品の価格として評価し、その後、広告費や競合他社の価格など他の要因を追加することで、価格設定が売上に及ぼす影響を要因間の関係も含めて分析できます。これにより、最適な価格戦略を特定し、収益を最大化することに役立ちます。
階層的重回帰分析における課題・注意点
重回帰分析と同様、多重共線性や過剰適合などの課題があります。さらに、モデル構築における変数の選定や入力順序は仮説に基づくことになるため、仮説における間違いやバイアスなどの課題もあります。
階層的重回帰分析が有効となる条件
階層的重回帰分析が有効となる条件は、通常の重回帰分析と同様です。また、特定の変数や順序の仮説がある場合に適切です。
3. パス解析(Path Analysis)

パス解析の概要
パス解析は、さまざまな要因や変数の関係性を視覚的に示し、それらの関係が結果にどのように影響を与えるかを理解する方法です。この手法の目的は、要因間の関係を明確にし、特定の出来事や結果における影響を理解することです。また、モデルを活用して要因間の影響を視覚的に表現し、統計的な関係を評価します。パス解析は、さまざまな要因や変数を図表で表現し、それらの要因が結果にどのように影響を与えるかを示します。要因間の関係性を矢印で表現し、結果における影響の程度を評価します。
活用例:顧客体験の向上
現代では、顧客とブランドの間でウェブサイト、モバイルアプリ、またはオフラインなどのさまざまな接点を通じて無数のやり取りが行われています。初期の接点(例:ソーシャルメディア、ウェブサイトなど)から、中間のステップ(例:商品レビュー、価格比較、営業など)を経てコンバージョン(例:購入、ダウンロード、ニュースレター登録など)まで、パス解析を活用することでカスタマージャーニーをより深く理解することができます。また、経路(パス)の中で、顧客の生涯価値を向上させる重要な接点を特定することで、リソースを最適化し、コンバージョン率の向上やプレミアム商品のアップセルなど、費用対効果の最大化を図ることができます。
パス解析における課題・注意点
主な課題は、最適なモデルを設計すること、多変量正規分布の仮定であること、潜在変数(直接は観察されないが、観測された他の変数から推定される変数)の取り扱いが不可であることです。
パス解析が有効となる条件
パス解析は、変数間の因果関係について仮説をもって明確に定義された理論モデルがある場合や、全ての変数が観測可能である場合に適しています。
4. ロジスティック回帰分析(Logistic Regression Analysis)

ロジスティック回帰分析の概要
ロジスティック回帰分析は、ある出来事や結果が発生する確率を調べる方法です。具体的に、特定の出来事が発生するかどうかを予測したり、理解したりするために活用されます。この分析の目的は、2つです。1つ目は、特定の出来事が発生する確率を予測すること。もう1つは、どの要因がその出来事の発生に影響を与えるかを理解することです。ロジスティック回帰分析は、さまざまな要因(説明変数)が特定の出来事の発生(目的変数)にどの程度影響を与えるかを数学的にモデル化します。モデルは確率を表す式として表現され、要因が発生確率にどのように関連しているかを示します。
活用例:顧客セグメンテーション
ロジスティック回帰分析は、顧客セグメンテーションに役立てることができます。例えば、オンラインショップでは、顧客が特定の製品を閲覧し、カートに入れ、最終的に購入するかどうかを予測するのにロジスティック回帰分析を活用できます。この情報をもとに、顧客の購買意向を理解し、広告やプロモーションの配信や商品のリコメンドを最適化することができます。顧客が購入の最終段階に進む要因や特性を把握することで、販売効率の向上と収益の増加が期待できます。
ロジスティック回帰分析における課題・注意点
目的変数と説明変数の間は、非線形な関係が仮定されています。また、信頼できる結果を得るためにはサンプルサイズが大きいことが必要です。説明変数が多い場合は、過剰適合が問題になることもあります。
ロジスティック回帰分析が有効となる条件
目的変数がバイナリで(「はい」または「いいえ」のようなカテゴリーであること)、説明変数と目的の関係が非線形であると仮定される場合に有効です。
5. 共分散構造分析(Structural Equation Modeling/SEM)

共分散構造分析の概要
共分散構造分析は、さまざまなデータの関係性を調べ、データ間の因果関係や相関を理解する方法です。この分析の目的は、データのパターンや構造を理解し、異なる変数がどのように関連しているかを理解することです。また、モデルを活用して、データの背後にある潜在的な因果関係を特定することもあります。共分散構造分析は、さまざまな変数の観測データから、それらの変数間の構造をモデル化します。モデルには観測されたデータと潜在的な因果関係を示すパスが含まれます。
活用例:調査結果の解釈
共分散構造分析は、調査結果の解釈に役立てることができます。例えば、消費者調査を行った場合、共分散構造分析を活用して異なる質問項目や調査項目の間の関係性を明らかにすることができます。これにより、特定の広告施策が顧客の購買意向にどのように影響を与えるかを理解し、製品の特性や価格と購買行動との関連性を評価できます。共分散構造分析を活用することで、マーケティング戦略の改善やターゲット消費者の特定に繋げることができます。
共分散構造分析における課題・注意点
共分散構造分析は、大きなサンプルサイズと複雑な仮説を必要とします。適切なモデルの特定と構築が難しく、統計理論に関する専門的な知識を持っている人と、仮説をしっかりと持っている事業ドメイン知識のある人を揃えることが重要です(統計理論だけでも、事業ドメイン知識だけでも不十分です)。他の手法も同じことが言えますが、共分散構造分析はとくにこれが顕著です。
共分散構造分析が有効となる条件
パス解析と同様で、変数間の因果関係について仮説をもって明確に定義された理論モデルがある場合に適しています。
6. ARIMA(自己回帰和分移動平均)モデル

ARIMAモデルの概要
時系列分析の主なモデルとして、ARIMA(自己回帰和分移動平均)は、時間とともに変動するデータのパターンやトレンドを理解し、未来の予測を行う手法です。このモデルの目的は、時間に関連するデータの変動やパターンを理解し、将来の出来事やトレンドを予測することです。また、モデルを活用して、データの背後にある因果関係や影響を明らかにすることもあります。
活用例:需要予測
ARIMAモデルは、マーケティング分野における需要予測に活用できます。例えば、過去の売上データをもとにARIMAモデルを活用して将来の需要を予測し、この予測をもとに商品の発注量や在庫管理を最適化することで、需要の変動に効果的に対応することができます。ARIMAを活用することで、在庫の過不足を減らし、効率的なサプライチェーン管理を実現します。
ARIMAモデルにおける課題・注意点
データの定常性(時系列データの統計的な特性(平均、分散、自己相関など)が時間によらず一定であること)を前提としていますが、現実では必ずしもそうではない場合もあります。また、データに季節性がある場合も課題となります。
ARIMAモデルが有効となる条件
データに定常性がある場合、時系列データの分析に適しています。
7. 状態空間モデル(State-Space Model)

状態空間モデルの概要
状態空間モデルは、時間の経過とともに変化するデータを理解するための手法です。このモデルは、データの中に含まれる隠れた要因や状態を推定するのに活用されます。このモデルの目的は、データの背後にある隠れた状態やトレンドを特定し、将来のデータを予測することです。また、モデルを活用して、データの変動や周期性などの特徴を理解することもあります。状態空間モデルは、データの観測値と、それらのデータの背後にある状態を表すモデルから成り立っています。モデルは通常、時間の経過に伴う変化を捉え、データの変動や予測に役立ちます。
活用例:在庫管理
状態空間モデルは、在庫管理に活用できます。例えば、商品の在庫状況を把握し、需要の変動に対応するのに活用できます。このモデルを用いて、過去の販売データや在庫レベルをもとに将来の需要を予測し、適切な在庫レベルを維持します。これにより、在庫コストの最適化や在庫切れの回避に貢献し、効率的な在庫管理が実現できます。
状態空間モデルにおける課題・注意点
主な課題は、潜在変数の存在によるパラメータ推定の難しさです。
状態空間モデルが有効となる条件
「状態」(現在の状態)と「観測値」(その状態を観測した値)を持つ時系列データの分析に適しています。また、ARIMAよりは状態空間モデルはARIMAより柔軟性があり、データに必ずしも定常性を仮定していないため、幅広い時系列パターンに適用でき、複雑な動的システムを捉えるのに適しています。
8. ベイジアンネットワーク(Bayesian Network)

ベイジアンネットワークの概要
ベイジアンネットワークは、事象や要因の関係を視覚的に表現し、確率的な推論を行うための方法です。この手法は、さまざまな出来事や要因が互いにどのように影響を及ぼすかを明確に示します。この手法の目的は、事象や要因の関係を理解し、特定の出来事が発生する確率を計算することです。また、モデルを活用して、異なる要因が結果に与える影響を予測することもあります。ベイジアンネットワークは、さまざまな要因や出来事をノード(節点)として表現し、これらの要因間の関係を矢印(エッジ)で示します。確率分布を使用して、出来事が発生する確率を計算し、モデルを活用して情報の伝達と推論を行います。
活用例:新商品開発
ベイジアンネットワークは、新商品開発に活用できます。例えば、企業が新商品の特徴や価格設定を検討する際、ベイジアンネットワークを活用して市場の反応を予測します。このモデルを利用することで、異なる商品特徴や価格設定の組み合わせが市場でどのように受け入れられるかを評価できます。また、競合他社の戦略や市場状況との関連性も考慮し、最適な新商品戦略を策定します。ベイジアンネットワークを用いることで、新商品の成功確率を向上させ、リスクを最小限に抑えることが可能です。
ベイジアンネットワークにおける課題・注意点
ベイジアンネットワークの構造をデータから学習するのは、特に大規模なネットワークの場合は計算コストが高くなる手法です。信頼できる結果を得るためには、十分な量のデータが必要です。
ベイジアンネットワークが有効となる条件
MCMC法と同様に、ビジネス用途・目的において、確率理論と不確実性をモデリングする必要がある場合に有効です。変数間の確率的関係をグラフ形式(ネットワーク)で表現するのに適しています。
終わりに
統計モデルは、マーケティングに透明性、予測精度、意思決定のサポートをもたらします。
ただし、モデルの選択は、解決したい課題と利用できるリソース(知識、時間、データ)によって変わります。ビジネス側とデータサイエンティストが連携し、課題を正確に理解して適切なモデルを選ぶことが、成功の鍵です。
マーケティングの実態を完璧に表現できる統計モデルはありません。しかし、確信を持ってアクションにつなげるには、これらのモデルを有効活用することが不可欠です。
データサイエンティストがモデルの精度を検証し、調整することが極めて重要です。信頼性のあるデータと正確なモデルを組み合わせることで、マーケティングの最適化を実現できます。
統計モデルに関するよくある質問(FAQ)
Q1. 統計モデルを使うには、高度な数学の知識が必要ですか?
実務で統計モデルを活用する場合、すべての人が数式を理解する必要はありません。大切なのは、各モデルの特徴と適用場面を理解することです。
実際の分析はデータサイエンティストが担当し、マーケティング担当者は課題の定義と結果の解釈に注力するという役割分担が一般的です。両者が協力することで、最大の成果を生み出せます。
Q2. どのモデルを選べばいいか分かりません
モデル選択は、以下の3つの要素で決まります。
解決したい課題
- 予測したいのか、要因を理解したいのか
- 結果は数値か、2択か、それとも時系列データか
利用できるデータ
- サンプル数は十分か(最低でも数百件、理想は数千件以上)
- データの種類(数値、カテゴリー、時系列)
- データの質(欠損値や異常値の有無)
リソース
- 分析にかけられる時間
- 利用できる専門知識
- 予算
迷った場合は、まず重回帰分析やロジスティック回帰分析といったシンプルなモデルから始めることをお勧めします。
Q3. 統計モデルの結果は、どれくらい信頼できますか?
統計モデルの信頼性は、以下の要素に左右されます。
データの質
- サンプル数が十分か
- データに偏りがないか
- 欠損値や異常値が適切に処理されているか
モデルの適切性
- 課題に対して適切なモデルが選ばれているか
- モデルの前提条件が満たされているか
- 過剰適合や過小適合が起きていないか
検証プロセス
- 予測精度が検証されているか
- 複数のデータセットで確認されているか
完璧な予測は不可能ですが、適切に構築されたモデルは、勘や経験だけよりも高い精度で意思決定をサポートできます。定期的にモデルの精度を検証し、必要に応じて調整することが重要です。
Q4. AIや機械学習との違いは何ですか?
統計モデルと機械学習は、目的とアプローチが異なります。
統計モデル
- 要因と結果の関係を理解することに重点
- 「なぜそうなったか」を説明できる
- 比較的少ないデータでも機能する
- 結果の解釈がしやすい
機械学習
- 予測の精度を最大化することに重点
- 「何が起こるか」を予測する
- 大量のデータが必要
- ブラックボックスになりやすい
マーケティングでは、両方を使い分けることが効果的です。要因を理解したい場合は統計モデル、純粋に予測精度を高めたい場合は機械学習が向いています。
Q5. 結果をどう経営層に説明すればいいですか?
統計モデルの結果を経営層に説明する際は、以下のポイントを押さえましょう。
専門用語を避ける
- 「決定係数」→「モデルの当てはまりの良さ」
- 「有意水準」→「偶然ではないと言える確からしさ」
ビジネスインパクトを示す
- 統計的な数値だけでなく、売上や利益への影響を金額で示す
- 「相関係数0.8」より「広告費を10%増やすと売上が8%増える見込み」
視覚化を活用する
- グラフや図で直感的に理解できるようにする
- 複雑な関係性は、パス図などで可視化する
リスクと限界も伝える
- 予測の不確実性を正直に説明する
- どこまでが分かって、どこからが分からないかを明確にする
Q6. モデルの精度をどう評価すればいいですか?
モデルの評価方法は、モデルの種類によって異なります。
予測モデルの場合
- 予測値と実際の値の差(誤差)を測定
- データを分割して、未知のデータでの予測精度を確認
- 複数の指標(決定係数、二乗平均平方根誤差(RMSE)など)で多面的に評価
分類モデルの場合
- 正解率、適合率、再現率などを確認
- 混同行列で詳細な結果を把握
一般的な確認事項
- モデルの前提条件が満たされているか
- 異常値や外れ値が結果に影響していないか
- 過剰適合が起きていないか
最も重要なのは、実務での運用を通じて継続的に精度を確認し、改善を続けることです。
Q7. 分析結果が期待と違う場合、どうすればいいですか?
期待と異なる結果が出た場合、以下のステップで確認しましょう。
データを再確認
- 入力ミスや異常値がないか
- データの集計期間や範囲は適切か
- 欠損値の処理は適切か
モデルを見直す
- 選択したモデルは課題に適しているか
- 前提条件は満たされているか
- 重要な変数が抜けていないか
仮説を再検討
- 当初の仮説が正しかったか
- 見落としている要因はないか
- 市場環境の変化が影響していないか
予期しない結果は、新たな発見のチャンスでもあります。固定観念にとらわれず、データが示す事実を受け入れることが重要です。
サイカについて
サイカは、マーケティングのデータサイエンス領域で10年以上、国内エンタープライズ企業を中心に280社以上の支援実績があります。
多様な業界の専門知識を持つデータサイエンティストとコンサルタントが、統計手法を活用したデータドリブンな戦略の策定から、顧客理解、クリエティブ分析・制作、メディアプランニング、効果検証と予算の最適化まで、より良い意思決定を支えるデータ活用をサポートします。
貴社固有の課題・目標や、入手可能なデータに応じた最適な統計モデルの活用や分析支援について、ぜひお問い合わせください。