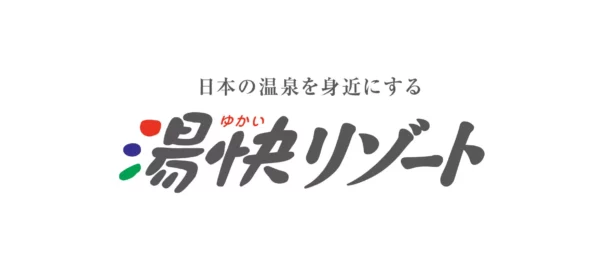丸亀製麺とサイカの取り組みは、ビジネスの勝率を高めるための“キードライバー”を解き明かす試みです。キードライバーを解き明かすことで、投資すべき先に対する考えがブレなくなり、意思決定のスピードが上がって、結果として事業の成長に繋がると南雲氏は考えています。同社では、もともと構築していたマーケティングモデルの解像度をさらに上げ、ビジネスを伸ばすキードライバーを明らかにする手段の一つとして、データサイエンスを活用しています。
サイカとのプロジェクトは、まずMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)を活用して商品プロモーションとブランディングの最適投資配分を解明する取り組みから始まりました。約半年のプロジェクトを通して、投資配分の最適解が見えてきた後、次に着手したのが商品が売れた背景・メカニズムを明らかにする取り組みです。これは、顧客が行動(購買)するまでに影響する意識をデータで明らかにするアプローチです。
本記事では、取り組みの前提となる丸亀製麺におけるマーケティングの考えと、サイカとの取り組みについて紹介します。
目次
丸亀製麺が実践する“KANDOドリブンマーケティング”
「顧客は集めるものではなくつくるものであり、“感動”こそが顧客を創造する源泉価値だと考えています。人は強く心が動かされるから(感動がある)こそ行動(購買)するのです」
(南雲氏)
南雲氏が語るこの考えのもと、丸亀製麺のすべての思考や行動は、“感動”を創造するために存在しています。同社のすべての戦略・戦術は「感動体験No.1」というビジョンの実現へつながるよう設計されています。そしてその源泉価値を、「一軒一軒が製麺所」「手づくり・できたてのおいしさ」「人の力」が織りなす感動体験と定義しています。これはマーケティング戦略だけでなく、商品戦略や営業戦略、DX戦略などすべてに当てはまることだそうです。
このように“感動”を意思決定の最優先事項とし、事業を持続的に成長させるためには、感性とデータの両立が必要だと南雲氏は考えています。データからは“感動”は創れない。感性だけでは確率が低い。そのため、両者を組み合わせてマーケティング戦略や戦術を組み立てていく取り組みを強化しています。これは丸亀製麺に息づく「二律両立※」という考え方に基づいたトレードオンを目指す姿勢の表れでもあります。
※予測不能レベルの進化を遂げるために、「二律背反」しがちな要素を「二律両立」させるという考え
実際、丸亀製麺のマーケティングコミュニケーションでは、左脳・理性へのアプローチを通して選ばれる理由やパーセプションを、右脳・直感へのアプローチを通して選ばれる衝動をつくっています。

丸亀製麺が実践する“KANDOドリブンマーケティング”
丸亀製麺が実践するハイブリッド戦略
――80%の売上はブランド力によって決まる
「当社はブランディングで右肩上がりのベースラインをつくり、フェア商品で衝動の山をつくるハイブリッド戦略をとっています。80%の売上はブランド力によって決まるものであり、ブランドに対する理解・好意度・共感が高まっている状態をつくることが最重要だと考えています。そのうえで1.5カ月ごとに年8回フェア商品を展開することで、食べたい衝動を最大化し、事業を持続的に成長させています」
(南雲氏)
南雲氏の説明の通り、同社ではブランディングとフェア商品のプロモーションを戦略的に組み合わせることで(ハイブリッド戦略)、右肩上がりのベースラインと定期的な衝動の山をつくっています。

ブランディングとフェア商品プロモーションのハイブリッド戦略のイメージ図
また、短期的に見ると顧客体験価値(CX)の積み重ねがブランド力につながると考え、カスタマージャー二―に沿った顧客接点ごとに「どこでどういう価値を感じていただくか」を顧客体験に落とし実践しています。その蓄積を可視化して関係部署と共有し、一体感をもって取り組んでいくために、データサイエンスを活用したアジャイルな高速アクションを大切にしています。
これらを実現するための、サイカとのプロジェクトにおいて以下2つの取り組みを行っています。
<取り組み①> 商品プロモーションとブランディングの最適投資配分の解明:ブランド・エクイティ分析
- ブランド・エクイティ分析とは?
- MMMの応用による長期にわたるブランド蓄積効果を加味した分析。丸亀製麺における「ブランディングで右肩上がりのベースラインをつくり、フェア商品で衝動の山をつくるハイブリッド戦略」の効果を可視化する取り組み。
- 分析の結果わかったこと
- 商品プロモーションによる短期スパイクとブランディングの長期蓄積の相乗効果で、狙い通り右肩上がりの成長が築かれていたこと。さらに、ブランディングによって商品CMの効果が押し上げられたことも判明した。
「きっと正しいだろうと感覚でわかっていたことが数値として可視化されたため、意思決定しやすくなったほか、新商品の広告予算を決める際にも役立っています」
(南雲氏)
事業成果につながる“キードライバー”は何か
――MMM×KSF分析による新たなアプローチ
<取り組み②> 事業成果につながるブランド重要指標を検証し、感性をデータで測る:ブランドKSF(Key Success Factor)分析
- ブランドKSF分析とは?
- 持続的に業績が高まる背景・メカニズムを明らかにする取り組み。アンケート調査データを使用し、来店に対するブランドKSF(ブランド重要指標)を解明し、また、そのブランドKSFに影響を及ぼす因子を解明する。
- 分析の結果わかったこと
- リピート/新規いずれにおいてもブランドKSFとして最も重要なのは利用意向であること、また、最も利用意向につながっているのは「うどんがおいしい」という認識であるということがわかった。
- その「うどんがおいしい」に直結するイメージとしては「安心して食べられる」と「他とは違う良さがある」が重視されており、丸亀製麺の源泉価値に近しい項目と相関関係があることもわかった。

丸亀製麺におけるKSF分析の概要
社内外の関係者とのコミュニケーションがスムーズに
このように、ブランディングの効果やブランドの重要指標を定量的に示すことは、戦略や戦術の根拠となるだけでなく、策定した戦略・戦術を実行に移す際にも非常に有用だと南雲氏は語っています。戦略や戦術の方針を社内外の関係者に浸透させるには、感性に訴えることが効果的な場合もあればデータを用いて理性に訴えることが効果的な場合もあります。特に後者を必要とする場面において、戦略・戦術に対する理解を促進することができ、各関係者とのコミュニケーションがスムーズになったそうです。
戦略に100%正解はないが、信じる道の解像度を高めたい
「戦略設計をするうえで、当然100%の正解はない」と南雲氏は語っています。ただ、信じる道の解像度を高めて未来を切り開いていくうえでは、拠り所となるものが必要であり、それが南雲氏がデータサイエンスを活用する理由だと説明しています。
また、戦術の面においても、環境の変化が激しい今日のマーケティングでは、感性とデータを行き交わせてアジャイルに最適化していくことの重要性がますます増しています。南雲氏は、この感性とデータを駆使する戦い方を、スポーツの世界でのデータ活用に例えて説明しています。
「スポーツの世界では、選手の状態や試合の展開を感覚で捉えながら、スコアや成功率のデータも見る必要があります。どちらか一方だけを見ていては勝てません。マーケティングにおいても、日々市場や消費者は変化しているので、感性とデータの両方を駆使していかないと戦いに勝てないのです」
(南雲氏)
まさにこれを実践する取り組みとして、丸亀製麺では「うどんスコア」と「体験スコア」を「丸亀感動スコア」として各店舗に毎日フィードバックしています。日々の店舗体験と顧客の感情を、データとしても蓄積・共有しているのです。※
※こちらはサイカとのプロジェクトの内容ではありません
このように、データを駆使してビジネスを推進している南雲氏は、MMMとの向き合い方やこのプロジェクトのパートナーとしてサイカを選んだ理由を以下のように語っています。
「MMMはあくまで目的ではなく手段であり、MMMですべてが解明できるとは思っていません。だからこそ、プロジェクトのパートナーには一緒に議論を通して正解を見つける姿勢を求めています。もちろん、パートナーに丸投げでは勝率が上がらないので、必ず自社で主導するようにしています。そのうえで、サイカをパートナーとして選んだ決め手は、スピード感とコンサルタントの向き合う姿勢です」
(南雲氏)
「スピード感」
日々変化するマーケティング環境に適応するためには、分析のスピードや頻度もそれに合わせて高める必要があります。同社のプロジェクトでは、MMMを四半期に1回のペースで分析しており、分析論点が追加になる場合は都度モデルを調整しながらPDCAサイクルを回しています。
「コンサルタントの向き合う姿勢」
100%正解がない世界において、解き明かしたい課題は次々と生まれてきます。また、環境の変化に伴い、論点もどんどんアップデートされます。それらに対し、柔軟にそして粘り強く寄り添う姿勢がパートナー選びの決め手となりました。
成長の先に目指す姿
――外食業界で働く人の存在意義を高めたい
――“食の感動で、この星を満たせ。”(トリドールのスローガン)
南雲氏が同社の成長の先に目指すのは外食業界全体の変革です。外食業界の消費者インサイトを解き明かすことで外食ビジネスを伸ばし、外食業界で働く人の存在意義や価値を向上させていきたいと語っています。

「数字ではなく、唯一無二の感動体験を創造し続けることを追求することで、必然として高い収益性と持続的な成長を実現できるということを証明したい」
(南雲氏)
こう語る南雲氏は、さらなる取り組みとしてEX(従業員体験価値)向上に向けたプロジェクトを進行しています。このプロジェクトは、従業員が働く幸せとプライベートの幸せを両立することで内発化が促進され、今まで以上に顧客に最高の感動体験を提供することができ、結果として事業成果に繋がるという考えに基づいています。この一連の流れをモデル化することで、再現性高く成果を出せる組織づくりを目指しています。
このように、新たなステージへと進化し続けている丸亀製麺の挑戦に、サイカは引き続き伴走していきます

丸亀製麺のプロジェクト変遷