〒106-0032
東京都港区六本木3丁目1-1
六本木ティーキューブ14F(受付14階) Google Mapで見る
© 2023 XICA CO.,LTD.

現代の競争社会。闇雲に戦っても到底勝ち抜けやしない。
そこで「データ」という武器を。
データは無機質で色がない。武器になるが、答えはくれない。
ではどうするか。
あなた自身が挑戦し、創造し、実現する。
そうすれば、データに色がつき、見え方が変わる。
あなたが進化し、才能が開花していく。
『サイカロン』は、データ分析のノウハウをはじめ、チャレンジするビジネスパーソンの挑戦心や創造力を掻き立てるコンテンツを幅広く取り揃えたWebマガジン。
データを自由に扱うビジネスパーソンへの飛躍を、いまここから。

ビジネスパーソンが知っておくべきデータサイエンスの基礎知識をわかりやすく説明|アルゴリズム、機械学習、ビッグデータとは?

【データビジュアライゼーションの基本⑤】プレゼン成功を目指すグラフ作りのポイント3選
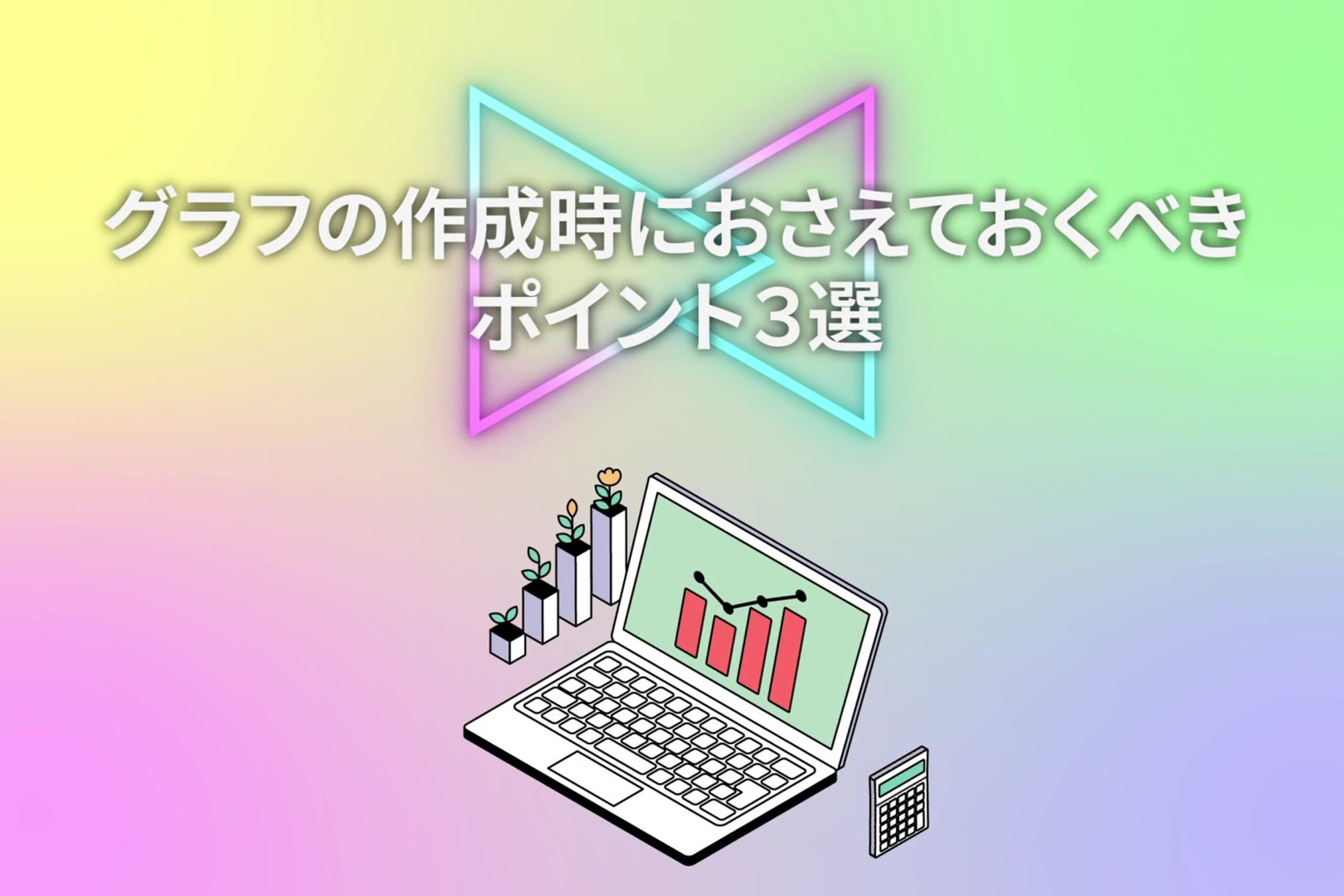
【データビジュアライゼーションの基本④】目盛り・凡例・軸ラベルで見やすいグラフを作るコツ

【データビジュアライゼーションの基本③】Excelグラフを訴求力あるデザインにする”時短技”

【データビジュアライゼーションの基本②】Excelのグラフはなぜわかりづらい?

【データビジュアライゼーションの基本①】ビジュアライゼーションの基本と各グラフの特徴

マーケターのための「現代のMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)」実践ガイド

費用対効果が最大となるメディアと広告媒体の選び方